来年の3月で15年間お世話になった職場を退職をする事になりました。
今までご指導いただいた諸先輩方、お医者さん、患者さん、先輩、後輩の皆様、誠にありがとうございます。今の職場の環境だったからこそ今の私が出来上がりました。感謝しております。
15年前、理学療法士の学生として今の職場に長期臨床実習でお世話になりました。
臨床も、教育も、研究も力を入れている藤元総合病院(前:藤元早鈴病院)。学生の身としても「ここはすごいところに来てしまったぞ」と焦ったのは良い思い出。
就職後、数年が経って当時のボスとお世話になった教授に「お前を入れるために学科長に根回ししておいてよかった」っとの悪巧み爆弾発言を頂き、その言葉が私の原動力となってます。
なんだかんだで進んだ大学進学と長く険しい博士号取得の道。妻の支えと子供達の癒やし、友人知人の応援もあってイバラの道のその先に到着することができました。
皆様本当にありがとです。
そのまま臨床研究家として現場に出続ける道も合ったのですが、ここ数年に出会った友人の生き方を見て、私が子供の頃に抱いていた夢を思い出しました。
「学校の先生になること」
彼は教育者として・研究者として「まなび続けること」が大切なことであることを教えてくれました。超大変そうですけど^^;
来年度より、宮崎を離れて、千葉の大学にて教鞭をとります。
私ができるご恩返しとしては、若輩者ながら経験値をお話すことしかできません。
15年間の取り組みから今の都城に残していけるもの、理学療法士としての思いと今後の展開ついてをいつものところで語ります。
残りの3ヶ月、宮崎・都城で頑張れるだけ頑張ります。
皆様これからもよろしくお願いいたします。






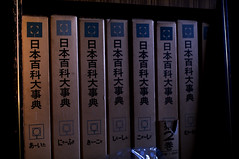

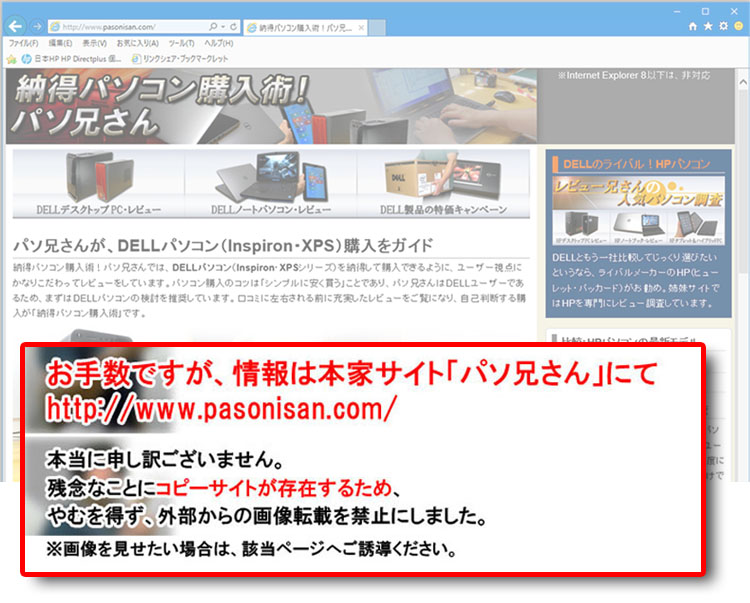
.jpeg)
















